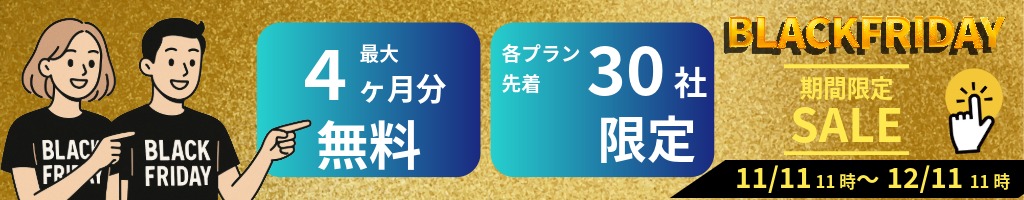
📋目次
はじめに
第1章:蔦屋重三郎は“江戸のコンテンツプロデューサー”だった
第2章:SNSも広告もない時代に「バズ」を仕掛けた方法
第3章:才能を見抜き、育て、売る──スターシステムの原型
第4章:ファンを巻き込み、市場そのものを広げた“体験設計”
第5章:「文化×ビジネス」を成立させた最初の民間マーケター
まとめ:蔦屋の戦略は、今も“使える原理”ばかり
はじめに
毎週日曜日、私は大河ドラマ『べらぼう』の世界に引き込まれています。
これまで主人公の蔦屋重三郎の存在をほとんど知らなかったのですが、ドラマを見続けるうちにどんどん虜になってしまいました。
なぜならドラマで描かれる蔦屋重三郎は、
ただの版元(出版社)ではなかったからです。
- 新人クリエイターを発掘し
- 市場に新ジャンルを生み
- 江戸の人々に“文化体験”を提供し
- 作品をブームに変え
- さらに次のスターを育てる
そう、蔦重は江戸のマーケターであり、プロデューサーであり、編集者であり、インフルエンサーだったんですよね。
この記事では、大河ドラマの世界観を楽しみつつ、
蔦屋重三郎の戦略が現代マーケティングにどう通じているのか?を一緒に考えてみましょう。
第1章:蔦屋重三郎は“江戸のコンテンツプロデューサー”だった
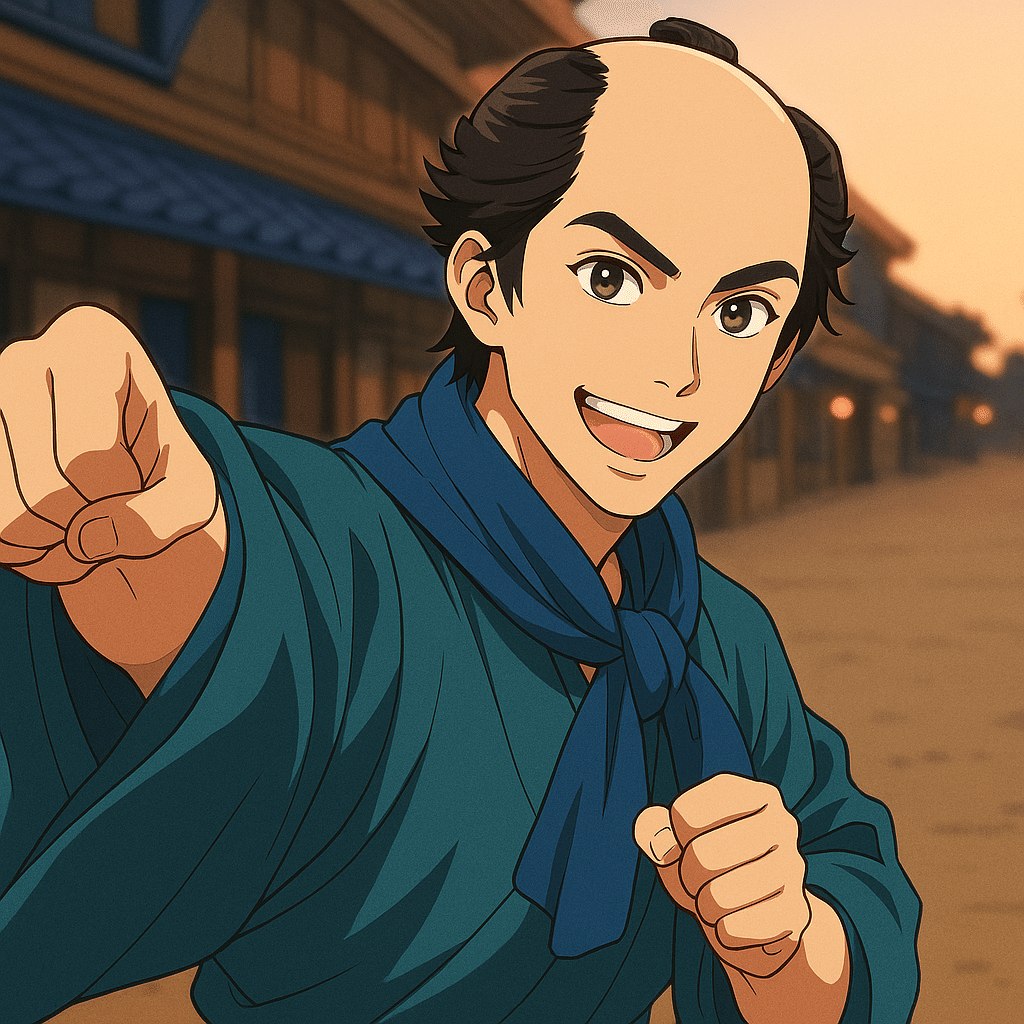
蔦重は、いま風に言えば Netflixのコンテンツ統括 + YouTubeプロデューサー + 出版編集長 を兼ねたような存在。
彼がやっていたことを現代語訳すると、こうなります。
- 「面白い人を見つける」
- 「作品を世に出す」
- 「人が集まる場をつくる」
- 「話題になる切り口を提案する」
- 「口コミを仕掛ける」
つまり、蔦重の本質は
“文化と人を編集して、市場をつくる人”。
今でいうマーケターの役割と完全に重なります。
彼は江戸の“文化OS”を再設計した人と言っても良いでしょう。
第2章:SNSも広告もない時代に「バズ」を仕掛けた方法
江戸には広告もSNSもありません。
なのに蔦重の作品は“街中で話題”になった。
その理由は、いまのバズ理論に通じる 3つの仕掛け にあります。
①「店舗=メディア化」
蔦重は自分の店を、ただの書店ではなく
“情報発信スタジオ” にしました。
- 新作を入口に並べる
- 常連が語り合える空間にする
- 「今これが面白いよ」を店ごと演出
→ 現代のApple Store/無印良品/蔦屋書店と同じ発想。
②「刺激 × 風刺」で話題性を生む
写楽・歌麿の浮世絵は、美しいだけではありません。
- 少しエロい
- 皮肉が利いている
- 世相を反映している
- 権力批判も織り交ぜる
SNSでバズる投稿と同じで、
“ちょっと刺激的で、共感を呼ぶ”のが蔦重作品の特徴。
③「口コミは“人が歩く”こと」
江戸の口コミは、SNSの代わりに
人が歩いて広げていました(まさに“フィジカル拡散”)。
蔦重は、
- 人が手に取って見せたくなる作品
- 見た瞬間に会話が生まれる内容
を作ることで、この“歩くSNS”を最大限に活用したのです。

第3章:才能を見抜き、育て、売る──スターシステムの原型
蔦重のすごさは、才能を見る目とプロデュース能力。
写楽、歌麿、山東京伝、馬琴など、
現代でいえば“文化界のレジェンド”を次々とデビューさせました。
現代マーケティングの言葉にすると──
●採用力
誰よりも早く“売れる前の才能”を見抜く。
●育成(オンボーディング)
作家を育て、作品を磨き、市場にマッチさせる。
●ブランド化
「写楽といえば蔦屋」
「江戸の人気作家=蔦屋ブランド」
というイメージをつくる。
これはまさに、
AKB48・K-POP事務所・YouTube MCN・アニメ制作委員会 と同じ構造。
蔦屋はスターを“つくり”、文化を“流行”に変えたプロデューサーでした。

第4章:ファンを巻き込み、市場そのものを広げた“体験設計”
蔦重が本当に天才だったのは、
“買う体験”を楽しくしたところ にあります。
- 店に行くことがイベント
- 新作を見るのが楽しみ
- 常連同士がつながる
- 蔦屋ブランドの作品を“コレクション”する
これ、もう完全に現代の
- Starbucksのサードプレイス
- Appleのデバイス体験
- 無印良品の世界観
- 公式ファンクラブの仕組み
と同じです。
蔦重は「本を売る人」ではなく、
“文化体験を売る人” だったのです。
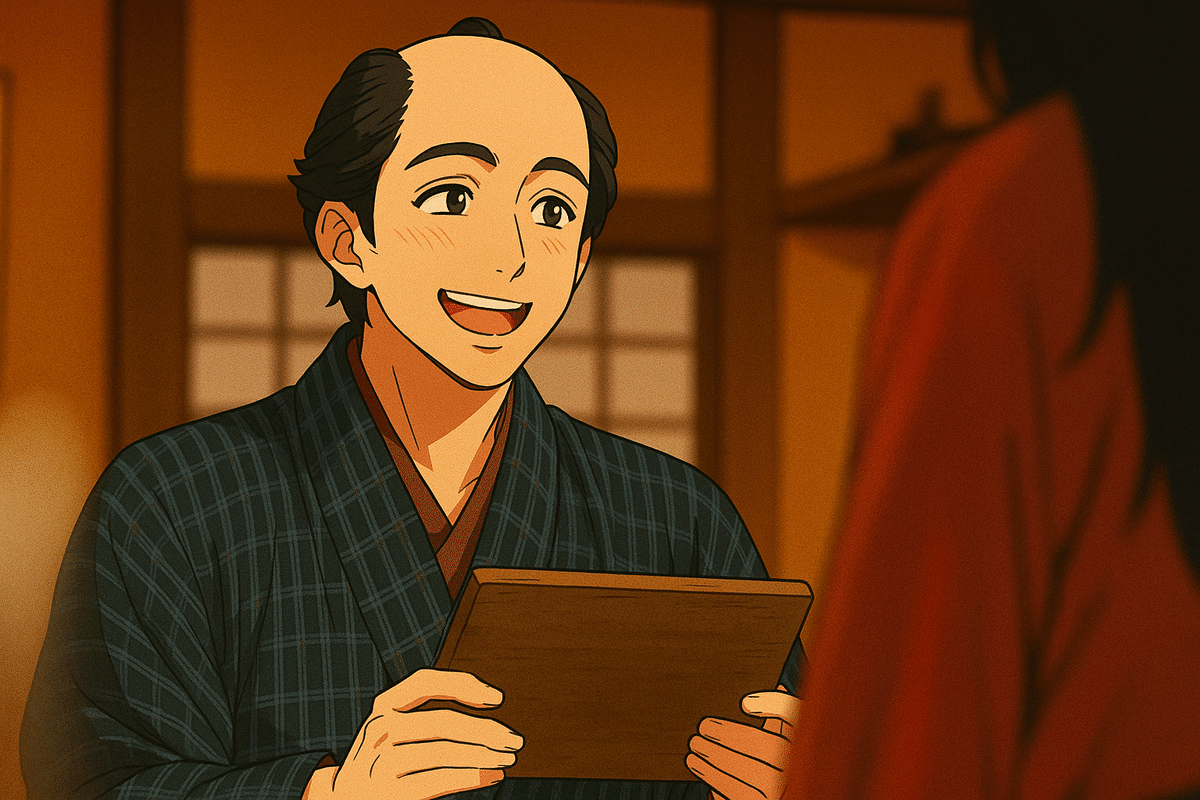
第5章:「文化×ビジネス」を成立させた最初の民間マーケター
蔦重の革新性はここに凝縮されています。
当時、文化(絵や本)は“お金になりにくいもの”でした。
それを蔦重は、見事に収益化してみせた。
- 人気作家を育て
- 作品をブランド化し
- ファンコミュニティを作り
- 市場を広げ
- 文化をビジネスにした
これって、現代の
- サブスク
- クリエイターエコノミー
- コンテンツビジネス
- ファンビジネス
- IP戦略
とほぼ同じ構造なんです。
つまり蔦重は“文化のDX”を江戸時代にやっていた人。
文化を“ビジネス領域”に引き上げた
日本最初の総合マーケターと言っても過言ではありません。

まとめ:蔦屋の戦略は、今も“使える原理”ばかり
いかがでしたか?
蔦屋重三郎の戦略は、
SNSも広告もネットもない時代に生まれたものなのに、
現代のマーケティング理論と驚くほど一致しています。
なぜか?
それは──
人が心を動かされる仕組みは、時代が変わっても変わらないから。
- 才能を見抜く
- 世界観を作る
- 話題化を仕掛ける
- コミュニティを育てる
- ファンを喜ばせる
すべて“普遍的な成功原理”です。
現代マーケターこそ、蔦屋に学ぶことは多いのかもしれませんね。
物語ももう終盤です。
これからさらに学ぶべきことがあるか、
しっかり見届けたいと思います!
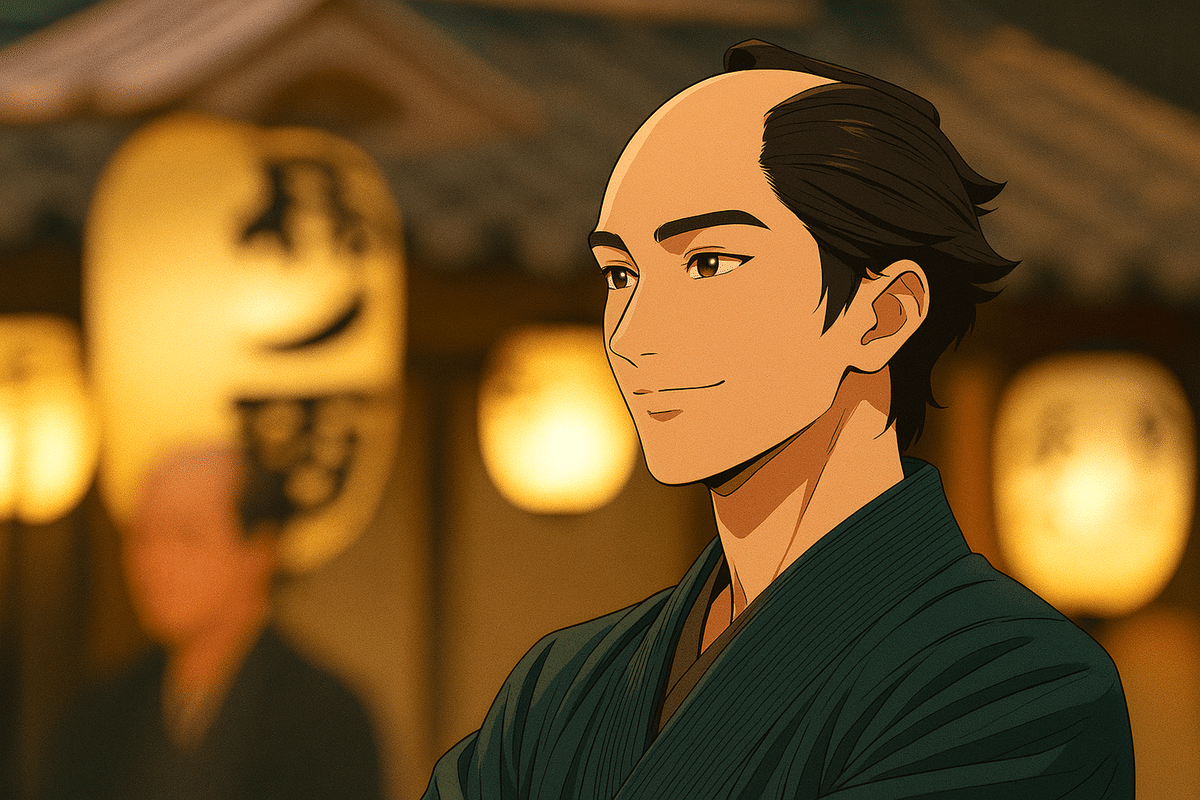
営業リスト作成にお困りではありませんか?

→ 成果を出す営業リスト3000件が無料で試せる👇
📝営業リスト収集ツール「リストル」https://www.listoru.com/


