もくじ
- はじめに
- 第1章:ChatGPTで記事は書けるのか?現実と誤解
- 第2章:AIライティングを使いこなす3つのコツ
- 第3章:AIと人間、どこまで任せてどこを手直しすべきか
- まとめ
はじめに
「AIでブログ記事が書ける時代になった」
そんな言葉を耳にして、「本当にそんなことできるの?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
実際、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場で、コピーライティングや記事作成のハードルは大きく下がりました。
でもその一方で、「なんか薄っぺらい…」「結局手直しが必要になる…」という声もよく聞きます。
本当にAIはライターの代わりになるのか?
使いこなすには、どんな工夫が必要なのか?
そして、“現場”で役立つツールなのか、それとも話題先行なのか?
この記事では、そんな疑問に対して、
- 実際に使ってみて感じるAIコピーの“リアル”
- 上手に使いこなすためのちょっとしたコツ
- 活用シーンと「ここは人がやるべき」境界線
を、わかりやすく整理してお届けします✍️
AIを“使いこなす側”に立てば、発信力と生産性は大きく変わる。
この記事が、あなたの武器をひとつ増やすヒントになればうれしいです!
第1章:ChatGPTで記事は書けるのか?現実と誤解
ChatGPTをはじめとする生成AIは、「誰でも簡単にブログが書ける」と注目を集めています。
確かに、テーマを入力すればスラスラと文章が生成され、「あっという間に記事ができる」体験をした方もいるでしょう。
でも現実は、「思ったより手直しが多い」「内容が浅い」と感じることも多いのが実情です。

❌ 誤解①:AIだけで“完成記事”が作れると思っていた…
多くの人が期待してしまうのが、「AIに任せればライター不要」という幻想。
実際には、以下のような課題が浮き彫りになります。
- 情報が浅く、専門性に欠ける
- 説得力のあるストーリーや論理展開が甘い
- ユーザー目線の構成になっていない
これはAIの限界というより、人間の入力(プロンプト)次第で大きく結果が変わるという構造があるからです。
✅ 現実①:記事の“素材”としては非常に有効
とはいえ、ゼロから考えて書く負担を減らせるのは事実。
たとえば、
- 見出し構成の叩き台を作る
- よくある質問のアイデアを出す
- 書き出しや締めのフレーズを提案してもらう
といった使い方では、ChatGPTは非常に頼りになります。
「骨組みはAI、仕上げは人間」という役割分担が、今のところ一番スムーズな使い方かもしれません。
💡 誤解②:「人間っぽく書ける」=「読者の心に響く」ではない
ChatGPTの文章は一見自然で、文法も正確。
でも、それだけでは読者に刺さる文章にはなりません。
読者の悩みに共感し、欲しい情報を届け、行動に導く。
この「読み手視点」は、今のAIにはまだまだ難しい領域です。
まとめると、ChatGPTは「記事の土台づくり」には強い味方。
でも、「心を動かすライティング」には、まだ人の手が欠かせないのが現状です。
第2章:AIライティングを使いこなす3つのコツ
AIを「思ったほど使えない…」と感じるか、「これは手放せない!」と感じるか。(私はもちろん後者タイプです。このブログもおおいにAIに手伝ってもらってます💦)
その差を分けるのが、“使い方の工夫”です。
ここでは、実際の活用者たちが実践しているAIコピー活用の3つのコツをご紹介します。

✔ コツ①:「誰に向けて書くか」を明示して指示する
AIは万能ではありません。
むしろ、人間が明確な“前提”を与えることで、アウトプットの質が大きく変わります。
例:
- 「40代女性に向けた美容記事」
- 「中小企業の経営者向けにIT導入の不安を解消する内容」
誰向けかを指定するだけで、トーンや用語、説得力が自然と変化します。
✔ コツ②:「書きたい構成」を最初に作ってから指示する
いきなり「ブログを書いて」と指示するより、見出しや章構成を自分でざっくり考えてからAIに渡すと、ぐっと精度が上がります。
おすすめの流れ:
- 目次を自分で決める(またはAIに提案してもらう)
- 各章ごとに「この内容を書いて」と依頼
- 生成結果に自分の視点を加えてリライト
こうすることで、“使えるドラフト”が出来上がりやすくなります。
✔ コツ③:「例え話」や「体験談風」に変換して深みを出す
ChatGPTは事実ベースの説明が得意ですが、やや平板になりがち。
そんなときは「例え話で説明して」「人間味を加えて」と追加指示を出すと、読みやすさと感情の共感がぐっと増します。
例:
- 「営業トークを料理に例えて説明して」
- 「この文章にユーモアを加えて」
→ 結果、より人間らしく、読者の頭に残る文章になります。
以上の3つのコツを押さえるだけで、AIライティングは“やや残念な仕上がり”から“十分使えるレベル”に進化します。
第3章:AIと人間、どこまで任せてどこを手直しすべきか
ChatGPTのようなAIが優秀になったとはいえ、完全自動で“読まれる記事”を作るのはまだ難しいのが現状です。
では、どの部分をAIに任せて、どの部分は人間が手を加えるべきなのでしょうか?
ここでは、実務的な視点で「分業の最適ライン」をご紹介します。
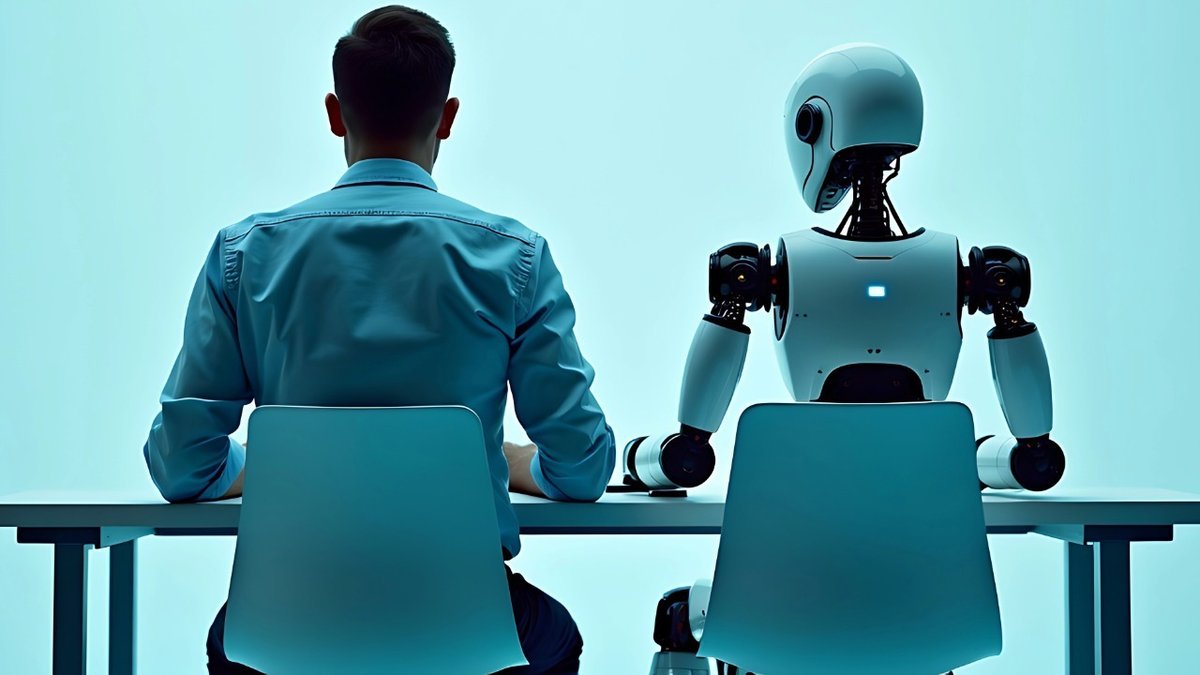
🤖 AIに任せてもOKな部分
● 叩き台としての構成案やドラフト作成
「とにかく最初の1行が出ない…」というとき、AIは優秀な補助輪になります。
目次案や各章の流れを提示させれば、執筆の足がかりになります。
● 一般的な説明や導入文
定義説明や一般的な背景説明など、情報が明確なパートはAIが得意とする部分。
定型的なパートは自動化することで時短になります。
● 誤字脱字チェックや表現の言い換え
リライトや推敲にも活用可能。口調のトーン変更も手早くできます。
🙋♂️ 人間が担うべき重要なポイント
● 読者の悩みに応える“企画力”
「なぜこの記事を書くのか」「誰のどんな悩みを解決するのか」
こうした記事の根っこは、人の視点が欠かせません。
● 具体例・実体験・ストーリー性のある部分
AIは一般論は得意でも、リアルな事例や感情をともなう話は苦手です。
ここに人間の手を加えることで、記事の“深み”が出てきます。
● 最後のチェックと信頼性の担保
事実の正確性や最新情報の反映、読みやすさのチェックは必須。
誤情報を避けるためにも、最終チェックは人の目で行いましょう。
AIと人間、それぞれの強みを知ったうえで「共同作業」のつもりで進めるのが、今の時代に合ったブログ制作スタイルです。
まとめ
AIコピーライティングの現実は、「すべて任せて終わり」ではありません。
でもだからこそ、上手に活用できる人にとっては、大きな武器になる時代が来ています。
今回お伝えした内容を振り返ると、
- ChatGPTは「素材作り」に最適な相棒
- 成果を出すには、「誰に何を伝えるか」を人間が設計すべし
- 書き上げた後も、信頼性と共感のチューニングが必要
この3つを意識するだけで、AIを“味方にできる人”と“使われる人”の差が広がることは間違いありません。
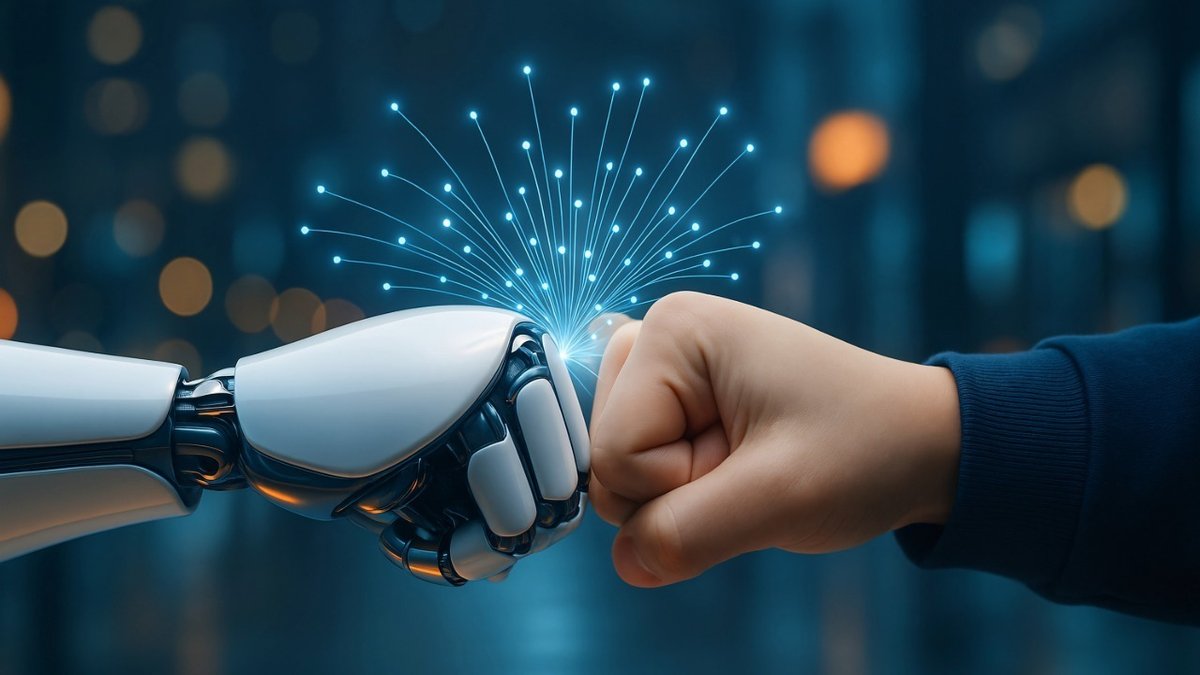
「AIだからこそ書けるもの」「人だからこそ伝えられること」
そのバランスを見極めながら、あなたの発信力をさらに高めていきましょう💡
まずは1本、AIと一緒に記事を作ってみるところからスタートです!
あなたの営業活動を応援します!
営業リスト作成にお困りではありませんか?

「広告費をかけても成果ゼロ…」それ、“売る相手”を間違えてるのかもしれません。営業成果は“リスト”で9割決まります。
→ 成果を出す営業リスト3000件が無料で試せる👇
📝営業リスト収集ツール「リストル」www.listoru.com



コメント