はじめに:0→1営業の“現実”は想像以上にハードだ
スタートアップの営業は、キラキラして見えるかもしれません。
最先端のプロダクト、フラットな組織、柔軟な働き方――
でも実際の現場は、そんなイメージとは裏腹に、泥臭くて、過酷で、正解が見えにくいものです。
特に“0→1フェーズ”と呼ばれる立ち上げ期の営業は、
「実績なし・信頼なし・認知なし」の三重苦。
顧客の理解を得るのにも一苦労で、何をすれば売れるのかさえ手探り状態です。
私も、あるスタートアップで営業の立ち上げを任されたとき、
「まず何から始めればいいのか」が本当に分かりませんでした。
- とにかくテレアポしてみる?
- とりあえず展示会に出てみる?
- いっそプロダクトを変える?
そんな混沌の中から、どうやって“初めの一歩”を切り開くのか。
そしてどうやってチームとして成果を出す形に持っていくのか。
このブログでは、0→1フェーズで成果を出すための「組織戦略」と「個人の動き方」について、リアルな視点でお伝えしていきます。
第1章:スタートアップ営業の特徴とフェーズごとの違い

営業は「売る」だけじゃない。それがスタートアップ
スタートアップの営業は、大企業の営業とはまるで違います。
まず、最初に立ちはだかるのは、「信頼の壁」。
- まだ誰も知らない会社
- 実績も事例もゼロ
- プロダクトも不完全
そんな状態で、顧客に「買ってください」と言うのは、正直かなり無茶があります。
でも、これが“0→1営業”のリアル。
営業は、ただ物を売るのではなく、「市場と顧客の声から、売れる形を作る」役割を担います。
フェーズによって求められる営業は変わる
スタートアップの成長は、大きく3つのフェーズに分けられます。
① 0→1フェーズ(プロダクト検証期)
- ゴール:売れるかどうかを確かめる(PMF)
- 主な営業活動:手探りで売り込み/ヒアリング/フィードバック収集
- キーワード:仮説検証、柔軟性、スピード重視
② 1→10フェーズ(再現性構築期)
- ゴール:売れる型を見つけて仕組みに落とし込む
- 主な営業活動:スクリプト作成、CSとの連携、CRM整備
- キーワード:プロセス、標準化、ナレッジ共有
③ 10→100フェーズ(拡大期)
- ゴール:営業組織をスケールさせる
- 主な営業活動:マネジメント、KPI運用、教育体制の構築
- キーワード:組織化、分業、再現性の担保
なぜ0→1営業は特別なのか?
それは、「営業がプロダクトを育てる立場」だからです。
- 顧客のリアルな反応を拾って開発にフィードバック
- 説明が通じない部分は資料や導入フローを改善
- 契約後のつまずきは、CSの仕組みごと見直す
つまり、営業が“プロダクトの仮説検証装置”として動くのがこのフェーズ。
ここで踏ん張れた営業が、その後の急成長フェーズでも中心になっていきます。
第2章:0→1を支える営業組織の在り方とは?
フレームより「人の柔軟性」がすべて
0→1フェーズの営業組織において、最初に知っておいてほしいのは、
「理想の営業プロセス」は存在しないということです。
なぜなら、まだ売れる形が定まっていないから。
このフェーズに必要なのは、フレームワークでもテンプレでもなく――
「柔軟に動ける人材」と「それを支える組織文化」です。
組織のキードライバーは「営業の仮説力」
どんな企業に?
誰が決裁者?
どんな悩みがある?
どこに刺さる?
いくらまでなら買う?
導入の障害は?
これらの問いに対し、営業が仮説を立てて動き、答えを市場から引き出す。
この動きが、そのままプロダクトと組織を進化させます。
つまり営業とは、“市場との対話役”であり、進化のセンサー”。

営業×開発×CS=「横断チーム」でこそ成り立つ
0→1営業で成果を出す組織には、共通して次のような特徴があります。
- 営業が開発に毎週フィードバックを上げている
- 商談メモを全員で共有して意思決定に活かしている
- 「これが売れ筋かも」の気づきが即プロダクトに反映される
こうした、“横断的に連携する文化”があるかどうかが成否を分けます。
営業だけが走っていても、成果には繋がりません。
チーム全体で「売れる形を作る」という空気を、いかに根付かせられるかがカギです。
組織戦略は“型”より“文化”
このフェーズでは、SFAやCRMといった営業ツールよりも、
「思いついたことをすぐ話せる」「失敗が許容される」空気感の方が大切です。
トライ&エラーが多い時期ほど、「小さな改善を素早く反映できる組織文化」が強い武器になる。
第3章: 個人として成果を出すための3つの思考法
“何もない”から始まるからこそ、営業の思考力が問われる
0→1フェーズで活躍できる営業パーソンに共通するのは、
「売り方を考えられる頭」と「動きながら考える姿勢」です。
「売れませんでした」で終わらず、
「なぜ売れなかったのか」「どうすれば売れるのか」を自問し続ける人が、
組織の未来をつくっていきます。
思考法①:仮説ベースで動く
- 「この業界にはこの課題があるはず」
- 「決裁者はきっと○○部長だ」
- 「メールより電話の方が通じやすいかも」
何をするにも、まず仮説を立ててから行動すること。
的外れなアプローチを減らし、学びのスピードが一気に上がります。

思考法②:PDCAでなく、DCAPで回す
0→1営業においては、いわゆるPDCAの順番が合いません。
D(Do)→C(Check)→A(Action)→P(Plan)
先にやって、反応を見て、改善して、次の仮説を立てる――
まずはやってみる型のPDCA(逆PDCA)が、このフェーズでは最も機能します。
思考法③:「売れない理由」を宝にする
- 価格が高い
- 導入のハードルが高い
- ニーズが噛み合っていない
こうした“断られた理由”こそ、最大の改善ヒント。
自分を責めるのではなく、プロダクトに還元する材料として蓄積することで、
営業としての信頼も、事業全体への貢献度も高まります。
「売る営業」から「売れる仕組みを作る営業」へ
0→1フェーズでは、「売れるかどうか」よりも、
「どうすれば売れるようになるかを発見できるか」が問われます。
自らが“マーケット探索者”となり、売れる型を見つけにいく。
それが、個人としての最大の価値提供です。
第4章:組織を巻き込む!営業から始まるプロダクト改善
売れない理由は、プロダクト改善の宝庫
「あと●円安ければ導入するんだけどね」
「セキュリティがもう少ししっかりしていれば…」
「●●との連携があれば便利なんだけどな」
こうしたお客様の“リアルな声”を聞けるのは、現場の営業だけ。
そしてそれこそが、プロダクトを強くする一番のヒントです。
営業が拾った声をどう活かすか?
成果を出すスタートアップの多くは、次のような仕組みを整えています。
- 営業が商談後に「フィードバックノート」をSlackやNotionで即共有
- 開発・CSと週1で共有ミーティングを実施
- 優先度が高い要望はすぐにプロダクトロードマップに反映
つまり、営業が拾った顧客の声を「一次情報」としてチーム全体で扱う文化があるのです。

「売る力」と「創る力」が融合したとき、最強になる
営業が“現場の目”を持って、
開発が“プロダクトの目”を持って、
CSが“導入後の目”を持って――
この三者が同じゴールを見て動くとき、
プロダクトは一気に“売れるもの”に進化します。
営業は単なる「売り手」ではなく、
顧客の声を社内に届けるエバンジェリスト(伝道者)でもあるのです。
営業の改善提案が、次の営業を楽にする
1回目の営業では通じなかったトークが、
プロダクト改善後にはスッと刺さるようになる。
この「変化」を一度でも経験すると、営業の仕事がどんどん面白くなります。
「売れない理由が減っていく」実感は、チームで成果を作っている証です。
まとめ:営業が“初速”を決める。0→1の本当の価値とは?
スタートアップにおける営業――
それは「売る」だけじゃなく、「作る」にも「育てる」にも関わる、極めてクリエイティブな仕事です。
- どんな企業が顧客になるのか?
- どんな言葉が刺さるのか?
- どうすれば導入に至るのか?
- なぜ、買ってもらえなかったのか?
この問いに、一番リアルに向き合えるのが、営業という存在。
💡 0→1営業が持つ、3つの大きな価値
- 売れる仕組みを見つける「マーケットセンサー」
まだ見ぬ顧客の反応を最前線で拾い、売れる型をつくる。 - プロダクトを進化させる「改善提案者」
導入ハードルや実運用の課題を開発に還元し、プロダクトを磨く。 - チームを引っ張る「最初の旗振り役」
曖昧だったターゲットや訴求を言語化し、全社の方向性を明確にする。
🧭 売れるプロダクトの背後には、必ず優れた営業がいる
市場にフィットしたプロダクトは、突然現れたわけではありません。
その背景には、顧客の声を拾い、動き、悩み抜いた“現場の営業”の力があります。
スタートアップ営業とは、
「会社の未来を形作る」最前線の仕事。
0→1の混沌の中で汗をかいたあなたこそ、次の1→10、10→100を引っ張る存在になるのです。

あなたの営業活動を応援します!

「広告費をかけても成果ゼロ…」それ、“売る相手”を間違えてるのかもしれません。営業成果は“リスト”で9割決まります。
→ 成果を出す営業リスト3000件が無料で試せる👇
営業リスト収集ツール「リストル」https://www.listoru.com/


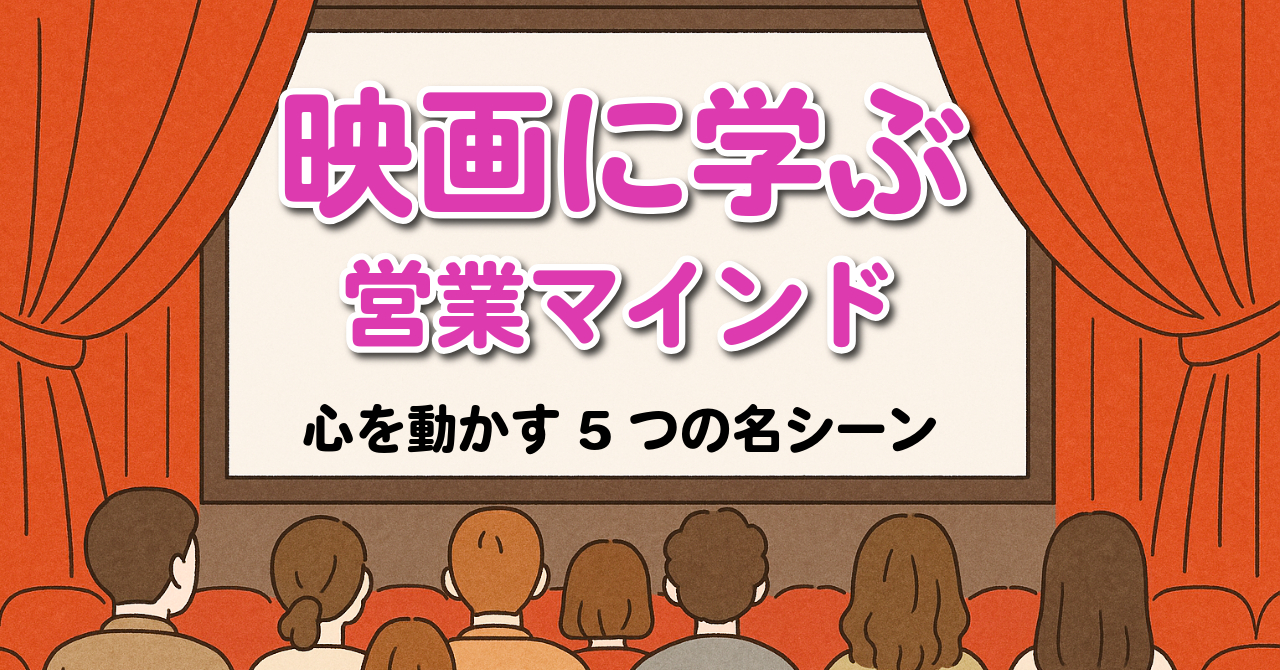
コメント